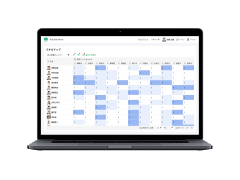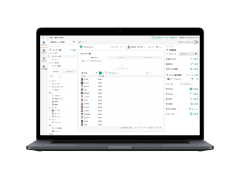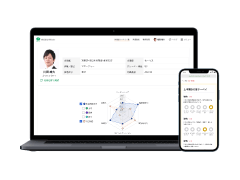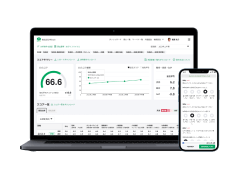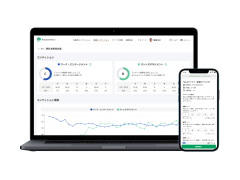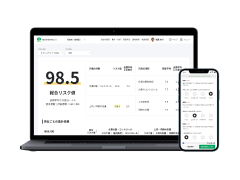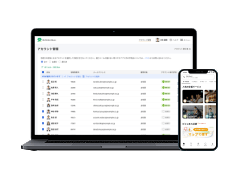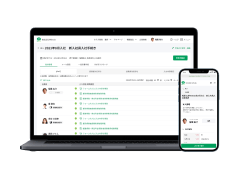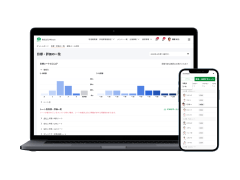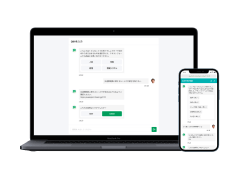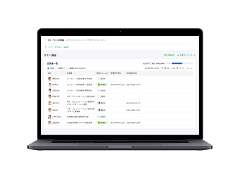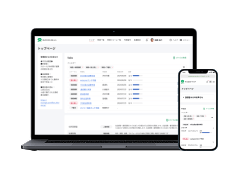過去最高益の裏にあった停滞感。JALUXが全社一丸で挑む、「自慢したくなる会社」への変革
株式会社JALUX 総務人事部 人財戦略課 課長
金田 仁男 様
株式会社JALUX 総務人事部 人財戦略課 上席主任
植田 恵美 様
- サービス業
- 501~1000名
- 従業員エンゲージメントを向上させたい
- 組織の課題把握・分析がしたい
- 組織診断サーベイ
HRBrain導入開始:2021年01月01日
過去最高益の裏にあった停滞感。JALUXが全社一丸で挑む、「自慢したくなる会社」への変革
- 課題背景
- 現在はコロナ禍が明けて業績は好調だが、そういった外部環境に左右されやすい航空・空港事業への依存度が高く、持続的成長のためには事業の多角化が求められていた。
- 業績は好調な一方、従業員のエンゲージメントは伸び悩み、「成長実感」や「働きがい」を持てているのかが不透明な状態だった。
- 従業員の意識が短期的な視点に偏り、イノベーションや新規事業の創出に必要な「未来志向」の文化が根付いていなかった。
- 打ち手
- 組織診断サーベイを導入し、「働きがい」や「成長実感」といった目に見えない組織の課題をデータで可視化。
- 施策の主体を人事から「現場の管理職」へとシフト。管理職に自組織のサーベイ結果を適切に読み取り、課題設定出来るよう研修を実施。
- 退職予兆の早期発見や、業績とエンゲージメントの相関関係の把握など、データを組み合わせることで、より戦略的な人事施策へと活用した。
- 効果
- サーベイのスコアが経営層から現場まで、組織の状態を客観的に議論するための「共通言語」となり、課題改善を目指す機運が高まった。
- 管理職が部下との面談やコミュニケーションの機会を意識的に増やすなど、現場での対話が活性化し、組織改善に向けた具体的な行動が生まれた。
- 感覚的・属人的な判断から脱却し、データに基づいた戦略的で効果的な人事施策の検討が可能になった。
「働きやすさ」のその先へ。「成長を実感できる」組織になるために
Q. まずは、貴社の事業内容と、直近の経営課題についてお聞かせください。
植田様:
当社はJALグループの商社として、航空・空港事業、ライフサービス、リテール、フーズ・ビバレッジといった多角的な事業を展開しています。おかげさまで、コロナ禍が明けてからは業績も回復し、直近では過去最高益を更新する状況にあります。
しかし、経営層も私たち人事も、この結果に決して満足しているわけではありません。今後のさらなる成長、もう一段上のステージに上がるためには、多くの経営課題があると考えています。具体的には、現在の航空・空港系事業に依存した状態から脱却し、非航空・空港事業をさらに多角的に展開していくことが不可欠です。そして、数十年先を見据え、全く新しい事業の種をまき、イノベーションに挑戦していく。従業員一人ひとりがそうしたチャレンジ精神を持つことが、今後に向けて最も重要だと捉えています。
金田様:
現在の好調な業績は、インバウンド需要の回復といった外部要因に支えられている側面が大きいのが実情です。これは裏を返せば、コロナ禍の時のように外部環境が変化すれば、業績はまた急速に落ち込みかねないというリスクを抱えているということ。だからこそ、航空事業一本足ではない、盤石な事業ポートフォリオを築かなければなりません。そのために、今ある事業の幅を広げることはもちろん、既存の枠に捉われない、新たな柱となる事業を育てていく必要があります。
Q. そうした経営課題の解決に向けて、組織や人財の面ではどのような課題を感じていましたか?
金田様:
従業員の「未来志向」をいかに醸成していくかが最大の課題でした。どうしても商社の営業は、目先の数字を追いかけがちになります。もちろん、とても大事なことなのですが、従業員の意識が短期的な視点に偏ってしまうと、未来への投資や新しい挑戦が生まれにくくなる。5年後、10年後、会社として何をすべきか。そこから逆算して今を考える思考が、組織全体としてなかなか根付きづらいという課題がありました。
社長も「文化づくり・人づくり」こそが重要だと頻繁に発信されています。従業員一人ひとりが成長を実感でき、一つ上の視野で仕事に取り組めるような組織文化をいかにしてつくるか。それが、「事業ポートフォリオの変革」という経営課題と直結する、私たちの人的資本におけるテーマでした。
Q. 「成長を実感」という言葉がありましたが、業績が好調な中でも、従業員の方々のエンゲージメントには課題があったのでしょうか?
金田様:
はい。正直なところ、業績が数字として伸びているため、組織の課題は見えづらい部分がありました。しかし、エンゲージメントサーベイを実施してみると、従業員が「この仕事を通じて、自分は成長できているのだろうか」といった、個人のキャリアに関する悩みを抱えていることが見えてきたんです。
離職率自体が著しく高いわけではないのですが、エンゲージメントスコアも、決して高くはない。他社平均の水準なので、もっと改善できるはずだと感じていました。業績は伸びているのに、社内の空気がそれに伴ってポジティブになっているかというと、そこまでは言い切れない。もっと一人ひとりがワクワクしながら自律的に働き、会社としてのエンジンを力強く回していきたい、という想いがありました。
また、以前当社は一部上場していましたが、現在は非上場です。上場時代はルールに則って様々な情報発信をしていましたが、非上場になってからは、そうした情報発信の強制力がなくなりました。結果として発信力が落ちてしまい、それが社内の求心力という面でマイナスに作用しているのではないかと感じていました。従業員にとっては、会社の向かう方向が見えづらくなったかもしれません。
Q. それらの課題に対して、理想としてはどのような組織像をイメージされているのでしょうか?
植田様:
私たちが重視していたのは、「働きやすさ」の先にある「働きがい」です。制度が整っていて働きやすい、というだけでは不十分で、仕事を通じて自己実現ができたり、チャレンジングな姿勢になれたり、やらされているのではなく自発的に取り組めている状態ですね。従業員一人ひとりが、そうした自己満足度の高い状態でいられる組織が理想です。
金田様:
私個人の想いとしては、従業員が周りの友人や家族に「うちの会社、こんなに面白い人たちがいて、こんな新しいことに挑戦してるんだよ」と、胸を張って自慢できるような会社にしたい、という気持ちが根底にあります。そういう会社は、きっと従業員がイキイキと働き、お互いを高め合うようなポジティブな循環が生まれているはずなんです。
人事主導から「現場主役」へ。全社のマインドを変えた仕組みづくり
Q. HRBrain EX Intelligenceを導入する以前は、どのような取り組みをされていたのでしょうか?
植田様:
当社は、比較的早い段階から「働き方改革」に着手してきました。フレックスタイム制度や、コロナ禍以前からのテレワーク導入、法定以上の子育て支援制度など、いわゆる「働きやすさ」というハード面の整備は手厚く行ってきたと自負しています。
ただ、それらの施策だけでは不十分だと感じていました。EX Intelligenceを導入し、サーベイの結果と向き合ったことで、ハーズバーグの言う「二要因理論」をまさに実感することになりました。つまり、「働きやすさ」という衛生要因の整備だけではエンゲージメントは本当の意味で向上しないということです。従業員が本当に求めているのは、キャリアについて上司と対話する機会や、会社の目指す方向性を自分ごととして捉える機会といった、よりソフトなアプローチでした。それこそが、仕事の満足度を高める動機づけ要因としての「働きがい」だったんです。
Q. 数あるサービスの中から、HRBrain EX Intelligenceを選ばれた決め手は何だったのでしょうか?
植田様:
まず、当社ではもともと人事評価やタレントマネジメントでHRBrainのシステムを導入しており、社員情報のメンテナンスや連携がスムーズである、という点が大きな理由です。
機能面では、単なるエンゲージメントスコアを出すだけでなく、「期待」と「実感」のギャップを分析するというロジックに非常に納得感がありました。これなら、表面的な満足度だけでは見えてこない課題の本質に迫れるのではないかと考えたんです。さらに、そのデータを毎年蓄積し、定点観測ができるという点も、継続的な改善活動を行ううえでとても魅力的でした。

※画像はイメージです
Q. 導入後、具体的にどのような取り組みを進められたのか教えてください。
植田様:
導入から3年、様々な取り組みを進めてきましたが、大きな方針転換は、施策の主体を「人事」から「各組織の管理職」へとシフトさせたことです。私たち人事だけで全社のエンゲージメントを上げることには限界がある。スコアを本気で動かすためには、組織単位、つまり現場でPDCAを回してもらうことが不可欠だと考えました。
そのために、まず部長層に対しては、人事部長が毎年サーベイ結果を基にした面談を実施し、組織の状態について対話する場を設けました。経営陣とも年に一度、2時間のディスカッションを行い、会社全体の課題として共有しています。
そして、最も重要なキーマンとして位置づけたのが、「課長職」です。プレイヤーである一般社員を直接束ねる課長こそが、現場の空気をつくる中心人物だからです。そこで、これまであまりサーベイ結果を深く共有できていなかった課長層に対し、組織改善の重要性やサーベイの読み解き方を伝え、自組織に対するアクションを考えてもらう研修を3回にわたって実施しました。さらに、今年度からは全管理職の目標設定の中に、「サーベイ結果を踏まえた組織改善の実践」という項目を新たに追加しています。
Q. 現場の管理職、特に課長の方々を主体とした施策に本格的にシフトされたんですね。
金田様:
はい。「管理職の最大のミッションは、個人の業績を上げることではなく、人財育成である」。私たちは、研修などを通じて、そう強く発信し続けています。現場の管理職が取り組まなければ、人事が何を言っても明確な成果は見込めないですからね。
もちろん、マインドチェンジは簡単なことではありません。特に営業の最前線にいる課長は、自身の数字も追うプレイングマネージャーが多く、「研修が多い」という率直な声が上がることもあります。それでも、私たちは「今までが少なすぎたんです」と伝え続けてきました。
実際に、ここ2〜3年で、組織管理職向けの研修は格段に増やしました。組織改善だけでなく、部下とのコミュニケーションの取り方、評価のフィードバックの仕方など、人やマネジメントに関するインプットの機会を、会社の教育体制として大きく変えてきたんです。こうした発信と機会の提供を続けることで、少しずつですが、組織の土壌、文化そのものが変わってきているという手応えは感じています。

「個の力」を次の事業の柱へ。サーベイをグループ全体の羅針盤にしたい。
Q. 実際にタレントマネジメントシステムとサーベイを同時に活用することで、どのような相乗効果を感じていますか?
植田様:
サーベイを実施してスコアが悪かった従業員は、その後退職に至る、という傾向が3年間のデータで掴めています。そのため、退職の予兆を少しでも早く察知するツールとして使っています。また、業績が振るわない部署はエンゲージメントスコアも低いという傾向が見えてきたので、組織改編の際の一つの客観的な材料にすることもあります。今後は、評価結果やハイパフォーマーとエンゲージメントの相関関係も分析していきたいですね。
金田様:
当社は単体では500名程度の会社なので、人事部員もある程度の期間いれば、社員の顔と名前、パフォーマンスは把握できます。しかし、担当者の異動やキャリア採用で新しく入ってくるメンバーもいます。そうした状況でも、タレントマネジメントシステムがあることで、誰もが同じレベルで社員情報を確認し、一貫性のある人事施策を検討できる、という点は非常に助かっています。
Q. 様々な取り組みを通じて、組織全体として何か変化はありましたか?
植田様:
定量的な成果として明確にお示しできるのはまだ少し先になりますが、定性的な面では確かな変化を感じています。最も大きな変化としては、管理職、特に課長が部下と接する機会、つまり面談やコミュニケーションの機会が格段に増えてきた実感があります。
これまでは、多忙な業務の中で後回しにされがちだった部下との対話が、サーベイ結果や目標設定をきっかけに「やらなければならないこと」として意識されるようになりました。例えば、サーベイで課題として見えた「企業理念の浸透」について、部の会議で話し合ったり、それを個人のキャリアとどう結びつけるかを1on1で対話したり、といった動きが各組織で見られるようになっています。
Q. 経営層の方々からの反響はいかがでしょうか?
金田様:
経営層も非常に高い関心を持って、この取り組みを見てくれています。サーベイ導入以前は、組織の状態を客観的な指標で把握することが難しかったのですが、今ではスコアという「共通言語」ができたことで、組織課題を具体的に議論できるようになりました。
これまで感覚的にしか捉えられなかった「組織の体温」のようなものが、経営における重要な指標の一つとして認識されたことは、非常に大きな一歩だと感じています。もちろん、スコアがすぐに劇的に変化するわけではありませんが、その推移を会社全体の重要事項として捉え、共に改善を目指すという機運が生まれているのが、何よりの成果だと思います。
Q. 最後に、今後の展望として、EX Intelligenceをどのように活用していきたいかお聞かせください。
植田様:
今後は、二つの方向で活用を広げていきたいと考えています。一つは、社内へのPRツールとしての活用です。サーベイを単なる組織改善のPDCAツールとして使うだけでなく、その結果や取り組みを従業員に積極的にアピールすることで、「会社は本気で皆さんと向き合っています」というメッセージを伝えて、組織全体の機運を高めていきたいです。
もう一つは、JALUXグループ全体への展開です。当社には多くの子会社がありますが、組織改善に対する熱量には、まだばらつきがあるのが現状です。私たちの取り組みを共有することで、グループ全体のエンゲージメント向上を牽引し、JALUXというブランド全体で組織の温度感を上げていく。そのためのツールとしても、活用していきたいと考えています。
金田様:
最終的に私たちが目指すのは、従業員一人ひとりの「個の力」が、自然発生的に新しい柱となる事業の種を生み出す組織です。従業員一人ひとりが自らの働きがいに向き合い、自発的に挑戦する。そのポジティブな循環が、会社の未来をつくっていくと信じています。そのための羅針盤として、これからもサーベイと共に、組織の変革に挑み続けたいですね。

※掲載内容は、取材当時の2025年7月時点のものです。