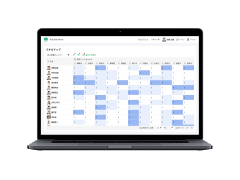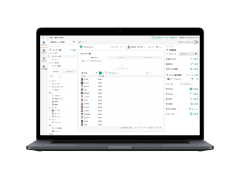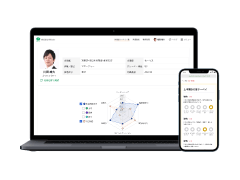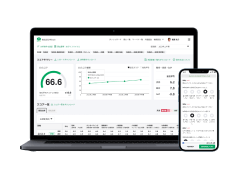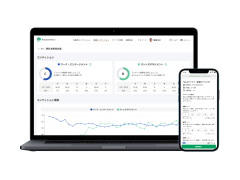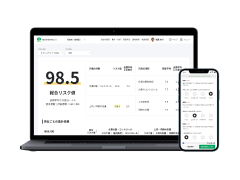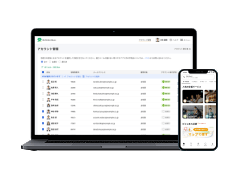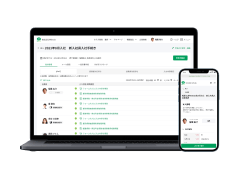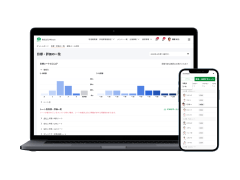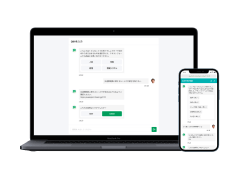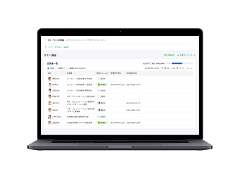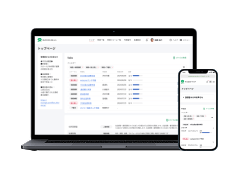1on1実施率が倍増、離職率は4.5%減。従業員の「過去と未来」をつなぐ、サーベイ起点の戦略的人事とは?
株式会社日比谷花壇 人事部 部長
向江 正智 様
株式会社日比谷花壇 人事部 Gリーダー
竹内 美香 様
- 卸売・小売業
- 1001名~
- 従業員エンゲージメントを向上させたい
- 組織の課題把握・分析がしたい
- 人的資本開示への準備がしたい
- 組織診断サーベイ
HRBrain導入開始:2021年10月01日
1on1実施率が倍増、離職率は4.5%減。従業員の「過去と未来」をつなぐ、サーベイ起点の戦略的人事とは?
- 課題背景
- 従来のタウンミーティングでは全従業員の“本音”を拾いきれず、従業員満足度調査も実施しただけで課題改善につながらなかった
- 事業の多角化が進む一方、部門間の連携が弱く、キャリアパスが固定化されやすかった。
- 会社の文化として「受け身」の姿勢が強く、従業員が自らのキャリアを主体的に考える風土が醸成されていなかった。
- 打ち手
- 「期待と実感のギャップ」を可視化できるHRBrainのサーベイを導入し、本質的な課題を科学的に特定。
- サーベイに加え、従業員のキャリア志向を問う独自の「バリューシート」を導入。
- サーベイ結果をもとに経営層を巻き込み、1on1の重要性を全社で共有。1on1の実施を各部署へ促した。
- 効果
- 施策の結果、サーベイスコアは72.5Pから73.4Pに向上。離職率は前年の12.5%から8.0%へと4.5ポイント改善。
- サーベイデータと個人の志向性を組み合わせることで、従業員の「過去・現在」と「未来」の両面から、データに基づいた配置・育成を検討する土台を構築した。
- 1on1の実施率が約40%から約80%に倍増し、従業員から「意見が言える風土になってきた」という声があがるなど、心理的安全性が向上。
「受け身」のキャリア形成を改善したいが、従業員の“本音”が見えなかった。
Q. まずは、日比谷花壇様の事業内容と、事業を取り巻く環境についてお聞かせください。
向江様:
当社は、「すべての明日に、はなやぎを。」というコーポレートメッセージのもと、全国でのフラワーショップ展開やオンラインでの販売はもちろん、ブライダル、ご葬儀、法人様向けの空間演出、さらには行政が管理していた施設を運営する地域創生事業など、多角的な事業を展開しています。
現在、特に力を入れているのが地域創生事業です。これは、行政が管理していた施設などの運営を我々が担い、これまで培ってきたホスピタリティを地域住民の方々に還元していくものです。全国で約80施設を運営しており、事業の大きな柱に育っています。
ただ、事業環境に目を向けると、変化の只中にあります。例えば、ブライダル市場では、コロナ禍を経て大規模な結婚式が減少し、一婚礼あたりの規模が小さくなる傾向にあります。また、ギフト市場においては、母の日もかつてはカーネーションを贈るのが一般的でしたが、今ではお菓子やコスメなど選択肢が増え、相対的に花の需要が変化しているのも事実です。一方で、コロナ禍以降にご自宅で花を楽しまれる「自家需要」が増え、私たちが始めたサブスクリプションサービスなども含め、新たな需要が生まれている側面もあります。
こうした需要の変化に加え、生産コストの上昇という課題もあります。お花はハウスで育てることが多く、そのための燃料費などが上がっています。生活必需品ではないからこそ、少しの値上げでもお客様の消費マインドに影響が出やすいため、企業努力でコストを抑えつつ、どう付加価値を提供し、新たな需要を創出していくかが大きなテーマになっています。
Q. そうした変化の大きい事業環境の中で、組織としてはどのような課題を抱えていらっしゃったのでしょうか?
向江様:
多くの事業を展開しているがゆえの課題がありました。各事業が独立して成長してきた半面、組織としては縦割りになりがちで、部門間の連携が十分ではありませんでした。そうなると、例えばブライダル事業で育った人材は、ずっとブライダル事業に、というようにキャリアパスが固定化されやすくなります。
また、企業文化として、どちらかというと「受け身」の姿勢が強かったと感じています。それがキャリアに対しても同じで、「会社から言われたから異動します」など、自らキャリアを考えるというよりは、会社からの辞令を待つ、という傾向がありました。
社会情勢が刻々と変化し、当社の事業領域が広がっていく中で、企業風土や従業員のマインドの変革へと繋げるため、「公平性・主体性・多様性」を掲げて2022年に人事制度を大きく改定しました。従業員が自分自身をプロデュースし、もっと主体的にキャリアを考えて行動できる組織を目指しました。

Q. 従業員の主体性を促すうえで、以前はどのような取り組みをされていたのですか?
向江様:
以前から、従業員の声を聞く取り組みは行っていました。例えば、役員たちが各地方の拠点に出向いて、現場の声を聞くタウンミーティングのような場を設けていました。しかし、それではどうしても「声の大きい人」の意見に偏りがちでした。物静かな人や、若手の率直な意見が埋もれてしまい、それが組織全体の総意であるかのように捉えられてしまう危険性があったんです。
また、ある事業部では離職率の高さが課題となり、独自に満足度調査を実施したことがありました。しかし、これは人事部が主導したものではなく、設問も統計的なロジックが組み込めておらず、調査をしたのみにとどまり、結果のフィードバックや具体的な改善アクションにはつなげられませんでした。いわば「実施しただけ」の状態です。
これでは、従業員の本音を引き出し、本質的な課題解決につなげることはできません。こうした過去の経験から、もっと科学的で、実効性のあるアプローチが必要だと痛感していました。
「実施しただけ」からの脱却。現場が主体的に動いて、1on1の実施率が倍増。
Q. 様々な課題意識があった中で、なぜHRBrainを選ばれたのでしょうか。
向江様:
いくつか決め手がありましたが、一番は過去の反省を活かせると感じたからです。まず、私たちは既にHRBrainのタレントマネジメントシステムを導入していたので、新たなシステムを入れることなく、既存の仕組みの中でサーベイを実施できるのは大きなメリットでした。
そして、何より魅力的だったのが、単なる満足度ではなく、「期待」と「実感」のギャップから組織の状態を分析できる点です。「従業員は会社に期待しているけれど、実感としては低い」項目こそが、取り組むべき本質的な課題ですよね。この考え方が非常に面白いと感じましたし、これなら「実施しただけ」にならず、具体的なアクションに繋げられると確信しました。また、他社平均と比較して自社のスコアがどうなのか、客観的な立ち位置がわかる点も決め手の一つでした。

※画像はイメージです
Q. 導入後、サーベイをどのように活用し、社内に浸透させていったのでしょうか?
竹内様:
まず意識したのは、サーベイを「一回きりのイベント」で終わらせないことです。第1回目のサーベイ結果が出た後、そのデータを事業部やエリアごとに細かく分けてフィードバックし、各部署の責任者に「今期の組織改善目標」を宣言してもらいました。
特に注力したのが、コミュニケーションの質と量を高めるための1on1の推進です。第1回目のサーベイ結果を分析すると、1on1を実施していない部署のスコアが低い、という明確な相関関係が見られました。この事実が、管理職の意識を変える大きなきっかけになりました。「1on1の実施が、結果として色々な数値につながっている」ということをデータで可視化することで、多くの管理職が「まずはやってみよう」と動き出してくれたのです。
向江様:
さらに、その動きを加速させるために、各事業部の1on1の実施状況を取締役会で毎月報告していきました。人事の報告パートで、各事業部の進捗を数値で提示することで、役員自らが実施状況を気にかけるようになりました。このトップダウンの働きかけと、現場の気づきという両輪がうまく噛み合ったことで、1on1の実施率は前年の約40%から、約80%へと劇的に向上しました。
Q. 1on1で対話の「量」が増えたんですね。さらに、独自の取り組みもスタートされたと伺いました。
向江様:
サーベイは、あくまで「過去から今」の状態を把握するものです。しかし、私たちが本当に実現したいのは、その先のタレントマネジメント、つまり、一人ひとりの未来のキャリアをどう支援していくか、ということです。そこで、サーベイと合わせて、私たち独自の「バリューシート」というアンケートを始めました。これは、「将来的にどんなことをやってみたいか?」という、従業員の未来の志向性を問うものです。
サーベイで組織全体の「今」の健康状態がわかり、バリューシートで一人ひとりの「未来」への想いが見える。この2つのデータが揃って初めて、私たちは勘や経験だけでなく、データに基づいて「この人は、本当はこういう事に挑戦したいのかもしれない」「この部署に異動すれば、もっと輝くのではないか」といった戦略的な配置や育成を考えることができるようになります。埋もれがちな一人ひとりの想いや強みをきちんと汲み取れる状態をつくることが、この仕組みの最大のポイントだと考えています。

離職率も大幅に改善。個人の挑戦を組織の力に変える、成長の好循環。
Q. 様々な取り組みを通じて、組織にはどのような成果や変化が表れていますか?
竹内様:
「働きやすさ」に関しては制度面での改善を行ったことで、明確にサーベイスコアが向上しました。全体的なスコアについては、72.5Pから73.4Pへと改善が見られました。離職率についても、昨年が12.5%だったのに対し、現状では8%程度まで低下しています。もちろんタイミングなど様々な要因はありますが、1on1を通じたコミュニケーションの活性化が少なからず良い影響を与えていると強く感じています。
定性的な面では、社内の空気が変わってきたと感じます。サーベイをきっかけに、従業員が「自分の意見を言ってもいいんだ」と感じられるようになり、心理的安全性が高まってきたという実感があります。
向江様:
経営層の意識も変わりましたね。以前はどこか画一的なマネジメントを是とする風潮もありましたが、サーベイを通じて部署ごとの課題の違いが明確になり、「組織や個人に合わせた多様なマネジメントが重要だ」という認識が浸透しました。今では「エンゲージメント」という言葉も当たり前に使われるようになり、管理職が部下のエンゲージメントをどう高めるか、ということに真剣に向き合っています。
Q. 今後の展望として、この仕組みをどのように発展させていきたいとお考えですか?
竹内様:
今後は、この取り組みを社外への発信にもつなげていきたいですね。サーベイの結果は、人的資本経営における重要な「非財務情報」です。私たちのエンゲージメントスコアや目指す方向性を社会に開示していくことで、採用において学生の皆さんにも魅力を感じていただけるはずです。そして、その開示内容は、今いる従業員たちも目にします。「自分の会社は、本気で働きがいのある職場を目指しているんだ」と感じてもらう。こうした社内外両方へのブランディングに活用していきたいです。
向江様:
私たちが理想とする組織は、手を挙げた人がきちんと称賛され、その挑戦を後押しできる組織です。従業員が「こんなキャリアを歩みたい」と主体的に考えてくれた時に、会社として「こんな道もあるよ」と多様な選択肢を提示し、実現できる環境を整えたい。サーベイとバリューシートで集まった「過去」と「未来」のデータを活用し、従業員一人ひとりのキャリア実現と組織の成長を結びつけていく。それが私たちの目指すタレントマネジメントの姿です。
従業員の主体的なキャリア形成を支援し、多様な経験を積める環境を整えることこそが、将来のリーダー候補を育てる土壌になると信じています。
Q. 最後に、同じように組織の課題に悩む人事担当者の皆様へメッセージをお願いします。
竹内様:
私が人事を経験する中でも、求められることはこの6年間で大きく変わりました。組織改善に終わりはなく、常に変化に向き合い、先を見据えた施策を考え続けなければなりません。それは本当に大変なことですが、そんな時にどうすればいいか一緒に考えてくれるHRBrain様のような信頼できるパートナーの存在は、非常に大きいと感じています。
向江様:
従業員は主体性を持ち、一人ひとりのビジョン達成に向けアクションを起こす。企業は公平性を担保し、頑張りを適正に評価をしていく「正のサイクル」を作る。そうすることで、キャリア自律した従業員と企業が互いに成長しあう事ができる「成長と分配の好循環」の実現をしていきたいです。そんな想いをもって、HRBrain様にもサポートしていただきながら、データを活用し、従業員一人ひとりと向き合い続けていきます。

※掲載内容は、取材当時の2025年7月時点のものです。